丂
OTOMO YOSHIHIDE TWIN PROJECT
2000 in HOKKAIDO
丂
|

|
|
Cathode乮僇僜乕僪乯
愇愳丂崅 sho (鈾)丂 SACHIKO.M (徏尨岾巕)
sampler with sine-wave丂 戝桭椙塸 electronics,
composition
Otomo Yoshihide's NEW JAZZ
QUINTET
媏抧惉岴 sax丂 捗忋尋懢 sax丂 悈扟峗復 acoustic-bass
朏奯埨梞 drums, trumpet丂 戝桭椙塸 guitar, electronics,
composition
仠戝桭椙塸
HP丂http://www.japanimprov.com/yotomo/yotomoj/index.html
|
|
|
|
NEW JAZZ QUINTET
嵍偐傜
戝桭丄朏奯丄捗忋丄悈扟丄媏抮
|
|
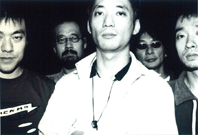 丂丂 丂丂
|
戝桭椙塸偺儖乕僣偺傂偲偮偱偁傞50乣70擭戙偺僕儍僘傪丄斵偺僋乕儖側帇揰偱嵞夝庍偟丄擔杮僕儍僘奅嵟嫮偺儊儞僶乕傪偦傠偊偰撈帺偺峔憿偲傾儞僒儞僽儖傪惗傒弌偡丄戝桭偑弶傔偰僕儍僘偵挧傫偩僾儘僕僃僋僩丅擔杮偺僕儍僘僔乕儞偺慡偰偐傜傕拲栚傪廤傔偰偄傞榖戣偺僌儖乕僾丅99擭壞怴廻PIT-IN
偱婙梘偘屻丄11寧儓亅儘僢僷僣傾亅丅懡朲傪嬌傔傞儊儞僶乕偺僗働僕儏乕儖挷惍傕擄偟偔丄杒奀摴僣傾乕偼崙撪弶偺僣傾乕偲側傞丅
|
|
|
|
|
|
|
CATHODE
嵍偐傜
戝桭丄SACHIKO.M 丄愇愳
|
|
 丂 丂 丂 丂 丂丂 丂丂
|
|
|
|
僄儗僋僩儘僯僋僗偵傛傞悽奅嵟愭抂偺壒偲丄擔杮偺揱摑妝婍偱偁傞乽鈾乿偺梙傜偓傪廳偹偨丄壒嬁揑偱枹棃揑側拲栚偺僒僂儞僪丅偄偪偼傗偔拲栚偟偨僕儑儞丒僝乕儞偑丄帺屓偺儗乕儀儖
TZADIK 偐傜CD儕儕乕僗偟偨丅
CD亀CATHODE亁TZADIK(暷崙)/TZ-7051乧'99擭儕儕乕僗
|
|
|
|
|
|
|
杒奀摴僣傾乕擔掱
|
|
|
|
丂
|
|
丂
|
|
|
9/9 SAT
撓彫杚
NEW JAZZ
QUINTET only
傾儈僟條乮昞挰1挌栚
榓岝價儖乯
奐墘/19:30乣丂
慜攧寯/\4,000 摉擔/\4,500
庡嵜丒 偍栤偄崌傢偣/傾儈僟條
丂丂丂啙 0144-34-1947
|
9/10 SUN
塝 壨
NEW JAZZ QUINTET only
塝壨挰暥壔夛娰傆傟偁偄儂乕儖
奐墘/18:30 奐応/18:00
慜攧寯/\2,000 摉擔/\2,500乮僼儕乕丒僪儕儞僋晅乯
崅峑惗埲壓/\1,000 (梫曐岇幰摨敽)
庡嵜/壒妝嵗
偍栤偄崌傢偣/ 杫懞
丂丂丂丂丂 啙 01463-2-3077
|
9/11 MON
嶥 杫
NEW JAZZ QUINTET &
CATHODE
儀僢僔乕丒儂乕儖
(拞墰嬫撿4惣6 惏傟偽傟價儖B1
啙 011-221-6076乯
奐墘/19:00 奐応/18:30
慜攧寯/\3,800 摉擔/\4,300
係僾儔丄戝娵丄儎儅僴奺僾儗僀僈僀僪
偵偰敪攧拞
庡嵜 / FM僲乕僗僂僃乕僽丂NMA
偍栤偄崌傢偣/ NMA
丂丂丂丂丂 啙 011-742-3458
|
9/12 TUE 孃 楬
NEW JAZZ QUINTET &
CATHODE
孃楬寍弍娰傾乕僩儂乕儖
奐墘/19:00 奐応/18:30
慜攧寯/\3,000 摉擔/\3,500
摿暿岞墘 [戝桭椙塸僜儘]
9/13 WED 僕僗僀僘
奐墘/19:00丂擖応椏/\2,000
乮扐偟12擔偺敿寯帩嶲 \1,000乯
庡嵜 / Kushiro Factory
偍栤偄崌傢偣/ 僕僗僀僘
丂丂丂丂丂 啙 0154-22-2519
|
丂
NMA 偺儈儗僯傾儉2000
丂
20悽婭丄NMA偺僼傿僫乕儗偼戝桭椙塸TWIN PROJECT
2000偲偄偆偙偲偵側傞丅
丂巚偊偽戝桭椙塸偺嶥杫偱偺弶儔僀僽偼丄1990擭3寧5擔丄婏偟偔傕偪傚偆偳10擭慜丅応強偼嶥杫墂杒岥偵
偁偭偨儔僀僽僴僂僗丒僯儏乕僆儕儞僘僋儔僽偩偭偨丅3戜乮偩偭偨偲巚偆偑乯偺僞乕儞僥乕僽儖偐傜敪偡傞僄
僢僕偺偒偄偨僲僀僘壒偑揦撪傪岎嶖偡傞丅摉帪偺戝桭偼傑偭偨偔柍柤偱丄媞偼変乆偺拠娫偲婄尒抦傝偲偱10
恖偩偗丅
丂偲偙傠偑偦偺儔僀僽偑埲屻10擭娫偺NMA偺妶摦偲曽岦偵戝偒側堄枴傪帩偮偙偲偵側傞偲偼丄偦偺摉帪偼巚
偄傕傛傜偸偙偲偩偭偨丅
丂儔僀僽偑廔傢傝丄傗偑偰偦偺徴寕揑側壒妝偺庺敍偐傜夝偐傟偨偙傠丄巹偼拠娫偺媞偺傂偲傝偵乽偄偭偟傚偵
墘偭偰傒側偄偐乿偲偦偦偺偐偟偨偺偑丄僺傾僯僗僩曮帵屗椇擇偩偭偨丅嫟墘偟偨戝桭偼曮帵屗偺嵥擻傪尒敳偒
乽搶嫗偱墘憈偡傞婡夛傪嶌傝傑偡丅乿偲栺懇偟丄摨擭8寧曮帵屗偼攡捗榓帪偵徯夘偝傟丄攡捗丄戝桭傜偲偲傕
偵怴廻僺僢僩僀儞偺僗僥乕僕偵棫偮偙偲偵側偭偨丅曮帵屗椇擇偑悽奅傊偼偽偨偔僗僞乕僩偲側偭偨偺偩丅
丂偄偭傐偆丄摉帪偐傜奀奜偺愭塻揑傾乕僥傿僗僩偨偪偲僱僢僩儚乕僋傪奼戝偟偰偄偨斵偼丄僨償傿僢僩丒儌僗丄
僕儑儞丒儘乕僘僇乕儖丒僗僩乕儞丄儃僽丒僆僗僞乕僞僌丄儅儖僞儞丒僥僩儘傗丄擔杮偺愭塻揑傾乕僥傿僗僩偨
偪傪巹偵徯夘偟丄嶥杫偱嫟墘丄帪偵偼杒奀摴傪僣傾乕偡傞傛偆偵側偭偨丅
丂傑偨丄'93擭僪僀僣丒儊乕儖僗丄'97擭僀僞儕傾丒傾儞僕僃儕僇偺僼僃僗僥傿僶儖偱丄戝桭椙塸偺妶桇傇傝傪
尒偰偒偨巹偼丄戝桭傗悽奅拞偺偡偽傜偟偄傾乕僥傿僗僩偨偪傪丄偙偺嶥杫偵丄偱偒傟偽擔杮偵徯夘偟偨偄偲偄
偆嫮偄徴摦偵嬱傜傟丄偦傟傑偱6擭娫拞抐偟偰偄偨乽僫僂儈儏乕僕僢僋丒僼僃僗僥傿僶儖丒僒僢億儘乿傪93擭
偵戞3夞傪嵞奐丄枅夞戝愒帤傪書偊側偑傜丄傛偣偽偄偄偺偵偲巚偄側偑傜戞6夞97擭傑偱懕偗偰偟傑偭偨丅
丂巹偑戝桭椙塸偲抦傝崌偭偨偺偼1984擭傑偱偝偐偺傏傞丅屒崅偺僊僞儕僗僩偲偄傢傟偨屘丒崅桍徆峴斢擭偺
杒奀摴弶傔偰偺僣傾乕偱丄斵偑塣揮庤偲偟偰摨峴偟偨帪偱偁傝丄偦偺帪偺婬偵尒傞恀潟側僊僞乕彮擭偺巔偵庝
偐傟丄埲屻岎怣偑懕偒丄'90擭偺弶儔僀僽偵寢傃偮偄偨偙偲偼摉慠偺惉傝峴偒偩偭偨丅
丂巹偼偮偹偵僋儕僄僀僥傿僽側傾乕僥傿僗僩偵嫽枴傪庝偐傟傞丅戝桭椙塸偼傑偪偑偄側偔僋儕僄僀僥傿僽偩丅
偮偹偵帺暘偺峴偔摴傪揑妋偵扵偟媮傔曄杄偟懕偗偰偄傞丅偩偐傜堦帪偨傝偲傕栚偑偼側偣側偄丅丂慜夞'98擭
偺乽I,S,O,乿偐傜2擭丄偦偺娫偵斵偼偳偙傑偱峴偭偪傑偭偨偺偩傠偆丅偦傟傪妋偐傔傞偙偲偑偱偒傞偺偑崱偩
偲偄偆巚偄偱丄嶐擭棃僠儍儞僗傪偆偐偑偭偰偄偨僣傾乕傪婇夋偟偨丅
丂変乆壒妝僼傽儞偵怴偨側姶摦傪惗傒丄戝桭椙塸偺壒妝偑偝傜偵21悽婭傊偼偽偨偔愡栚偺杒奀摴僐儞僒乕僩
僣傾乕偵側傞偙偲傪怱偐傜婅偄丄奆偝傫偺棃応傪偍傑偪偟偰偄傑偡丅
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂NMA丂徖嶳
丂
丂
丂
仠戝桭椙塸 乧
嶌嬋丄僞乕儞僥乕僽儖丄僊僞乕丄僄儗僋僩儘僯僋僗
丂1993擭丄僪僀僣丒儊乕儖僗丒僯儏乕僕儍僘嵳偵帺屓偺乽GROUND
ZERO乿偱弌墘丄敧愮恖偺戝娤廜偲僕儍乕僫儕僗僩偵愨巀偝傟丄埲屻奀奜
偺愭塻揑側壒妝嵳傪偼偠傔偲偡傞僔乕儞偱偼晄壜寚偺懚嵼偲側傞丅97擭偺儓乕儘僢僷丒僣傾乕傪嵟屻偵惿偟傑傟偮偮傕僌儔儞僪僛儘傪夝嶶丅
偦偺屻偼乽I.S.O.乿傗乽Filament乿側偳偱丄扙僒儞僾儕儞僌巜岦傪嫮傔偰偄傞丅偝傜側傞斵偺怴偟偄曽岦惈偼丄埲屻悢夞偺墷暷僣傾乕偱傕崅偔
昡壙偝傟丄99擭11寧丄僆乕僗僩儕傾丒僂僃儖僗偱奐偐傟偨僼僃僗僥傿償傽儖乽Music
Unlimited '99乿偺僉儏儗僀僞乕傪扴摉偟丄斵偺恖慖偵
傛傝弌墘幰傪僙儗僋僩丅戝桭帺恎傕乽僯儏乕丒僕儍僘丒僋僀儞僥僢僩乿(偦偺懌偱墷廈僣傾乕)乽僲償僅丒僩僲乿乽儈僀儔偵側傞傑偱乿
(搰揷
夒旻偺彫愢乽儈僀儔偵側傞傑偱乿偵戝桭椙塸偑壒妝傪偮偗偨)丄僜儘側偳偱弌墘丄偦偺惉壥偼崅偔昡壙偝傟偨丅
丂堦曽偱偼塮夋壒妝偺嶌嬋傗丄奺壒妝帍忋偺昡榑傗僐儔儉偺幏昅側偳偦偺嵥擻偼懡婒偵傢偨傝丄尰嵼惂嶌拞偺憡暷怲擇娔撀丄愺栰拤怣丄彫愹
崱擔巕庡墘偺塮夋乽晽壴乿偱壒妝傪扴摉偟偰偄傞丅
丂廐埲崀偺庡側梊掕偼丄10寧僯儏乕儓乕僋岞墘丄僪僀僣丒僪僫僂僄僢僔儞僎儞尰戙壒妝嵳丄11寧儀儖僊乕丒僽儕儏僢僙儖2000丄01擭侾寧
儘儞僪儞丒Japan Festival
側偳偱丄偄傑擔杮偺愭塻揑傾乕僥傿僗僩偱偼嵟傕奀奜偱妶桇偟偰偄傞傂偲傝偱偁傞丅
丂杒奀摴偱傕丄悢夞偺僫僂儈儏乕僕僢僋丒僼僃僗僥傿僶儖丒僒僢億儘偵乽僌儔儞僪僛儘乿乽儈僀儔偵側傞傑偱乿側偳偝傑偞傑側儐僯僢僩偱妶
桇丄僼傽儞偼妋幚偵傆偊偰偄傞丅
丂
OTOMO YOSHIHIDE's NEW JAZZ
QUINTET
媏抧惉岴 乧 僒僉僜僼
僅儞丄僄儗僋僩儘僯僋僗
1963擭愮梩導惗傑傟丅崱杧峆梇偺乽僥傿億僌儔僼傿僇乿丄乽嶳壓梞曘僨儏僆PLUS乿側偳傪宱偰丄1995擭乽戝桭椙塸僌儔儞僪僛儘乿偵嶲壛丅
尰嵼偼3偮偺儕乕僟乕僶儞僪丄乽僗僷儞僋僴僢僺乕乿乽媏抧惉岴僩儕僆乿乽僨乕僩僐乕僗丒儁儞僞僑儞丒儘僀儎儖僈乕僨儞乿偺懠丄乽戝桭椙塸僯儏乕丒僕儍僘丒僋僀儞僥僢僩乿側偳偵嶲壛偟丄奀奜岞墘傕懡偄丅僗僞僕僆丒僾儗僀儎乕偲偟偰傕丄
僠儍儔丄僺僠僇乕僩丒僼傽僀僽丄彫愹崱
擔巕丄崱堜旤庽丄僐乕僓丒僲僗僩儔丄恏搰傒偳傝丄愺揷桽夘丄朶椡壏愹寍幰丄僴僀億僕側偳偺儗僐乕僨傿儞僌偵傕嶲壛丄偦偺撆偺偁傞懚嵼姶
偼懡偔偺僼傽儞傪帩偮丅傑偨丄傾僀僪儖岦偗嶌帉丄嶌嬋丄傾儗儞僕傕偙側偡側偳懡嵥丅
捗忋尋懢 乧
僒僉僜僼僅儞
1965擭惗傑傟丅拞妛帪戙偵僗僥傿乕價乕丒儚儞僟乕偲攇曈掑晇偵塭嬁傪庴偗偰傾儖僩丒僒僢僋僗傪巒傔傞丅妛廗堾戝妛嵼妛拞偵乽僕儑乕僕
戝捤WE丂THREE乿丄乽屆郪椙帯榊僷僷儔僢僐丒僶儞僪乿偱僾儘僨價儏乕傪壥偨偡丅
埲棃丄廰扟婤丄嶳壓梞曘丄拞杮儅儕丄婖栰惔巙榊丄嶁揷
柧側偳丄暆峀偄儈儏乕僕僔儍儞偲嫟墘偟丄偦偺幚椡傪崅偔昡壙偝傟偰偄傞丅
尰嵼偼乽廰扟婤僆乕働僗僩儔乿乽嶳壓梞曘僨儏僆丒僾儔僗乿乽懞
揷梲堦僆乕働僗僩儔乿乽埢屗抭奊僼儗儞僘乿乽戝桭椙塸僯儏乕僕儍僘僋僀儞僥僢僩乿側偳懡悢偺僶儞僪偱妶婂拞丅
悈扟峗復 乧
傾僐乕僗僥傿僢僋仌僄儗僋僩儕僢僋丒儀乕僗
1963擭惗傑傟丅嶉嬍導弌恎丅墶昹崙棫戝妛偵擖妛屻僕儍僘偵嫽枴傪帩偪壒妝妶摦傪奐巒偡傞丅86帺屓偺僌儖乕僾乽儘僂丒僽儘僂乿傪寢惉丅
95擭丄崱杧峆梇乽僥傿億僌儔僼傿僇乿偵壛擖丄96擭丄壛屆棽乮P乯乽怓傪廳偹偰乿(峔惉丗揤帣媿戝)
偵嶲壛丅96擭12寧偵帺屓偺僌儖乕僾
乽Low Blow乿偺僼傽乕僗僩丒傾儖僶儉乽僇僼僃偍偠偝傫乿傪儕儕乕僗丅
偦偺懠丄僕儑儞丒僝乕儞丄僄儕僆僢僩丒僔儍乕僾丄姫忋岞堦丄働僀
愒忛丄徏晽峼堦丄側偳條乆側僕儍儞儖偺儈儏乕僕僔儍儞偲偺儔僀僽丄僣傾乕丄僗僞僕僆丒儚乕僋丄摍乆乧乧丅尰嵼偼乽LowBlow乿傪拞怱偵丄
乽戝桭椙塸僯儏乕僕儍僘僋僀儞僥僢僩乿乽嶳壓梞曘 4G
儐僯僢僩乿乽媏抧惉岴
僇儖僥僢僩乿乽撿攷僇儖僥僢僩乿懠懡悢偺僶儞僪偱妶桇拞丅壏
偐偔僌儖乕價乕側僾儗僀偱枺椆偡傞丅
朏奯埨梞 乧
僪儔儉僗丄僷乕僇僢僔儑儞
1959擭暫屔導惣媨巗惗傑傟丅娭惣妛堾戝妛嵼妛拞傛傝娭惣偺僕儍僘丒僄儕傾傪拞怱偵墘憈妶摦傪巒傔丄柉懓壒妝偵傕孹搢偟丄僪儔儉偵尷傜
偢條乆側僷乕僇僢僔儑儞傪僾儗僀偡傞丅娭惣偱偼丄撪嫶榓媣丄僫僗僲儈僣儖偲乽傾儖僞乕僪丒僗僥僀僣乿傪寢惉偟丄崙撪奜僀儞僾儘償傽僀僓
乕偲偺嫟墘傪悢懡偔偙側偟偰偒偨丅偲摨帪偵搶嫗偵偍偄偰傕昡壙傪崅傔丄戝桭椙塸乽僌儔僂儞僪丒僛儘乿乽廰偝抦傜僘乿傗攡捗榓帪乽儀僣僯
僫儞儌丒僋儗僘儅乕乿偵傕嶲壛丅97擭偵搶嫗偵嫃傪堏偟丄棫壴懽旻偲懢揷宐帒偲偺乽TOY乿丄戝搰曐崕乮搰塖乯丄庰堜弐偲廰扟婤偲偺僩儕僆丄
戝桭椙塸僯儏乕丒僕儍僘丒僋僀儞僥僢僩丄撿攷僇儖僥僢僩摍偵愋傪抲偔偵偲偳傑傜偢丄斅嫶暥晇丄姫忋岞堦丄儗僫乕僪塹赓丄堦慩岾峅傗棃擔
偡傞儈儏乕僕僔儍儞偨偪偲偺僙僢僔儑儞側偳丄奺抧偺儔僀僽僴僂僗偵偰儃乕僟乕儗僗側妶摦傪峴側偭偰偄傞丅
丂
CATHODE
愇愳丂崅 乧 鈾 (偟傚偆)
忋抭戝妛堾嵼妛拞偵鈾傪巒傔傞丅鈾傪媨揷傑備傒丄朙塸廐偵丄夒妝崌憈傪幣桽桋偵巘帠丅尰嵼偼丄鈾偲惓憅堾暅尦妝婍偱偁傞乽堭(偆)乿傪
墘憈丅夒妝墘憈抍懱乽椸妝幧乿偵強懏偟丄崙棫寑応岞墘傪偼偠傔丄NY儕儞僇乕儞僙儞僞乕丒僼僃僗僥傿僶儖丄僼儔儞僗丒儖傾儞壒妝嵳丄僂
僀乕儞丒儌僨儖儞傪偼偠傔崙撪奜偺條乆側壒妝嵳偵弌墘丅堦桍宒丄崅嫶桰帯丄摗巬庣傜偺鈾偺偨傔偺尰戙嶌昳偺弶墘傪悢懡偔偙側偟偰偄傞丅
堦曽丄搰揷夒旻乣戝桭椙塸乽儈僀儔偵側傞傑偱乿偵嶲壛偟丄97擭偺僫僂儈儏乕僕僢僋丒僼僃僗僥傿僶儖丒僒僢億儘偵弌墘偡傞側偳丄偦偺廮
擃側僙儞僗傕拲栚偝傟偰偄傞丅
SACHIKO丒M 乧
僒儞僾儔乕丒僂僀僘丒僒僀儞僂僃乕僽
戝桭椙塸
GROUND-ZERO乮1998擭3寧夝嶶乯偱悽奅奺抧偺僼僃僗僥傿僶儖摍偱妶桇丅埲崀偼丄僒儞僾儔乕帺懱偑傕偲傕偲帩偭偰偄傞僥僗僩
僩乕儞傗僲僀僘惉暘傪嵞棙梡偟偨撈帺偺僒儞僾儔乕憈朄偱CD嶌昳傪師乆敪昞偟丄枅擭悢夞偺墷暷僣傾乕丅摿偵僒僀儞僂僃僀償偩偗傪巊偭偨
僜儘偼悽奅偱拲栚傪廤傔傞丅尰嵼偼揙掙偟偨扙僒儞僾儕儞僌傪巜岦偡傞戝桭椙塸偲偺乽Filament乿丄堦妝媀岝丄戝桭椙塸偲偺僄儗僋僩儘僯
僋僗懄嫽儐僯僢僩乽I.S.O.乿丄愇愳崅乮鈾乯丄戝桭椙塸偲偺乽
Cathode乿丄拞懞偲偟傑傞偲偺壒嬁僨儏僆丄媑揷傾儈偲偺乽COSMOS乿摍偱妶
摦丅
丂
仠戝桭椙塸幏昅僐儔儉乽JAM JAM
擔婰乿乮搶嫗傾僩儉帍楢嵹乯傛傝娭楢晹暘傪敳悎丂
丂
99.8.崋
仐寧仐擔 怴廻PIT INN偱NEW JAZZ
QUINTET偺婙梘偘岞墘丅杮奿揑偵JAZZ偵挧愴偡傞偺偼弶傔偰偺偙偲偩丅JAZZ傊偺垽忣傪崬傔偰偁偊偰屆傔偐偟偄柤慜偵偟偨丅偙偺20擭JAZZ偑朰傟偰偒偰偟傑偭偨丄偦偟偰僆儗偑岲偒偩偭偨50乣70擭戙偺JAZZ偑傕偭偰偄偨戝愗側壗偐偵丄崱偺帹偱僩儔僀偟偰傒偨偔側偭偨丅弶墘偲偟偰偼傑偢傑偢丅偱傕崱偺帹偑擺摼偡傞悽奅傪嶌傞偵偼帄傜偢丅栤戣嶳愊偩丅偑傫偽傠丅
丂
99.11寧斣奜曇乽WELS MUSIC UNLIMITED
1999乿
丂11寧3擔
廐偺儘儞僌墷廈僣傾乕傕拞斦慄偵偼偄傞丅儘儞僪儞偱偺悢擔娫偺屻丄僆乕僗僩儕傾偺僂僃儖僗巗偱峴傢傟傞僼僃僗僥傿僶儖"MUSIC
UNLIMITED"偵忔傝擖傟傞丅13擭栚偺崱夞偼巹偺摿廤偑慻傑傟偰偄偰丄帺暘帺恎偺偄偔偮偐偺僾儘僕僃僋僩偺懠偵丄巹偑儕僗儁僋僩偡傞壒妝壠偑懡悢廤傑偭偰丄3擔娫偵搉傝25傕偺弌偟暔偑斺業偝傟傞丅
丂1999.11.7丂巹偺怴僶儞僪NEW JAZZ
QUINTET傕偄偄墘憈傪偟偰偔傟偨丅巹偼傎偲傫偳僄僼僃僋僩傕捠偝偢偵僼儖傾僐偺傒偱墴偟捠偟偨丅JAZZ偲偄偆屆偄僼僅乕儅僢僩偺拞偵傕巹偵偟偐偱偒側偄偙偲偑偁傞偼偢偩丅晛抜偼JAZZ偺悽奅偵偄傞偙偲偺懡偄儊儞僶乕傕丄偙偺3擔娫偺怴偟偄壒妝懱尡偱丄埲慜傛傝偼帹偑傂傜偄偰偒偨墘憈傪偟偰偔傟偨丅偳偆傗傜嵟弶偺堦曕偑摜傒弌偣偨傛偆偩丅乮拞棯乯
丂埲忋僉儏乕儗僀僩傪偟偨巹偺栚偐傜尒偨堄尒側偺偱丄岲堄揑偡偓偨偐傕偟傟側偄偑丄偙傟偱傕偩偄傇峊偊傔偵彂偄偨偮傕傝偩丅婥偯偄偨恖傕偄傞偐傕偟傟側偄偑丄僉儏乕儗僀僩偺崪奿偼嶥杫偱2擭慜偵峴傢傟偨NOW
MUSIC
FESTIVAL傪偐側傝嶲峫偵偝偣偰傕傜偭偨丅偙偺僼僃僗僥傿僶儖傕偡偽傜偟偐偭偨丅偙偺帪偺儅儖僞儞丒僥僩儘丄SACHIKO
M,戝扟埨岹偲巹偺儔僀僽斦乽FORE
FORCUSES乿偺拞偵尒傜傟偨朑夎偑丄妋幚偵奐壴偟丄偝傜偵師偺庬傪惗傒弌偦偆偲偟偰偄傞丄偦傫側姶偠偩偭偨丅懡偔偺僼僃僗偑摨偠婄傇傟偱丄側傫偲側偔曐庣壔偟偰偄傞姶偑偄側傔側偄側偐偱丄偝偡偑偵巹傕僼僃僗偦偺傕偺偵戝偒側尪憐偼傕偆偄偩偄偰偄側偄丅偨偩丄戝岲偒側壒妝偵偐偙傑傟偰嬉戲側3擔娫傪偍偔傜偣偰傕傜偭偨偙偲偵偲偭偰傕姶幱偟偰偄傞丅乮埲壓徣棯乯
丂
99.12寧崋
仐寧仐擔丂偙偺僼僃僗偱OTOMO YOSHIHIDE'S NEW JAZZ
QUINTET傕墷廈僨價儏乕丄偦偺懌偱丄抁偄墷廈僣傾乕偵弌傞丅僆儗偑惓柺偐傜僲儞僄僼僃僋僩偺僕儍僘僊僞乕傪抏偔偩偗偱傕偙偭偪偱偼憡摉偺榖戣偵側偭偰偄傞偺偩偗傟偳丄偦傫側榖戣偩偗偱僶儞僪傪攧傞傛偆側傑偹偼偟偨偔側偄丅偳偆偣傗傞側傜丄惓柺偐傜扤偺傑偹偱傕側偄堦棳偺壒妝傪傗傜側偔偰偼傢偞傢偞僆儗偑僕儍僘傪傗傞堄枴偑側偄丅奺抧偱柤偆偰偺僆乕僈僫僀僓乕払偑掋嶡偵偒偰傗偑傞丅GROUND-ZERO偺僕儍僘斉傪婜懸偟偰傞傫偩偭偨傜偲偭偲偲婣傝傗偑傟丅側傫偰巚偄偮偮傕丄傑偩傑偩曄壔偟偒傟偢偵偄傞帺暘偑丄媞偺惙傝忋偑傝偲偲傕偵偱偰偔傞偺偑暘偐傞丅偱傕僆儗偑峴偔傋偒曽岦偼偦偭偪偠傖側偄偭偰偙偲傕廳乆彸抦偟偰偄傞偮傕傝偩丅僣傾乕偺嵟廔擔丅儅儕僼傽僫偱廤拞椡傪偆偟側偭偰偞傢偞傢偟偰偄傞偄傞僆儔儞僟偺媞丅偙傫側帪偼埲慜偩偭偨傜戝壒検偱嫮堷偵偩傑傜偣偰偄偨丅偱傕崱偦傟傪傗偭偨傜丄媞偵偙傃傞偺偲曄傢傜側偄丅儔僗僩偺20暘傪墇偊傞惷偐側嬋偺拞斦丄媞偺偞傢傔偒偺拞偵徚偊擖傝偦偆側壒検偱丄偦傟偱傕摪乆偲墘憈偱偒偨弖娫丄傗偭偲嵟弶偺僗僥僢僾傪僋儕傾偟偨婥偑偟偨丅恀寱偵尒偰偄偰偔傟偨壗恖偐偵偼丄杔傜偑傗傝偨偄偙偲偑揱傢偭偨偼偢偩丅
丂
Date: Sat, 11 Dec 1999丂
11寧枛偵搶嫗偵傕偳偭偰偒傑偟偨丅婣崙偟偰傒傞偲崱擭慜敿偵榐壒偟偨嶌昳乽CATHODE乿偑偲偳偄偰偄傑偟偨丅朚妝婍偲僄儗僋僩儘僯僋僗偵徟揰傪偁偰偨巹柤媊偺傾儖僶儉偲偟偰偼丄弶偺嶌嬋嶌昳偱偡丅嫗搒偺FMN偐傜敪攧偵側偭偨僜儘偺儈僯CD乽DEGITAL
TRANQUILIZAR乿偺2嶌昳偲丄偙傟偐傜儗僐乕僨傿儞僌偵擖傞NEW JAZZ
QUINTET偱偺壒妝偑丄崱尰嵼巹偑傕偭偲傕傗傝偨偄偙偲偱偡丅棃擭偼偙偺乽CATHODE乿偲乽NEW
JAZZ
QUINTET乿偲偄偆2偮偺僾儘僕僃僋僩傪傛傝廩幚偝偣傞傋偔丄崱拝乆偲峔憐傪楙偭偨傝丄偦傟偵昁梫側妝婍偺惢嶌偵偲傝偐偐偭偨傝偟偰偄傞偲偙傠偱偡丅媣乆偵偼傫偩偛偰傪庤偵偟丄埆愴嬯摤偟偰偄傑偡丅
丂
Date: Mon, 13 Mar 2000
仐寧仐擔丂NEW JAZZ
QIONTET偺儗僐乕僨傿儞僌丅僆乕僶乕僟僽傗曇廤偲偄偭偨丄偄偮傕側傜摉偨傝慜偺傛偆偵傗偭偰偄傞榐壒偺曽朄傪堦愗巊傢偢偵丄崱夞偼堦敪榐傝偵偙偩偭傢偭偨丅榐壒媄弍偱屻偐傜壒嬁傪偮偔傞偺偱偼側偔丄偁偔傑偱傾僐乕僗僥傿僢僋偺壒応偱偺壒偺嬁偒偁偄傪挳偒側偑傜丄懄嫽墘憈偱壒妝傪嶌傞偙偲偵偙偩傢傝偨偐偭偨丅僆儗偵偲偭偰偺JAZZ偲偼丄偦偆偄偆傕偺偩偲巚偆偐傜偩丅帋傒偑偆傑偔偄偭偨偐偳偆偐偼丄偄偮偐敪攧偵側傞偙偺傾儖僶儉傪挳偄偨恖偑敾抐偟偰偔傟傞偩傠偆丅
丂
丂
亙栠傞亜
丂

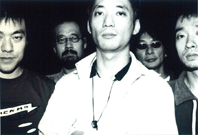 丂丂
丂丂 丂
丂 丂
丂 丂丂
丂丂